| 「あれー高尾?」 「おーひさしぶり」 「今帰り?」 「そ。そっちは?」 「わたしも部活終わって今帰り」 「一緒帰る?」 「うん」 「一ヶ月ぶりくらい?」 「そうかな、なんかもっと会ってる気もするけど」 「だな」 高尾とは家が斜向かいで、歳も同じということから物心付く前から一緒に過ごすことが多かった。 高校は別々になってしまったけれど、親同士も仲が良いからお互い会わずとも情報は入ってくる。 実際に会ったのは一ヶ月前くらい、朝偶然家から出るタイミングが一緒だった時だ。 「最近どうよ?」 「どうってどうもこうも特に何にもないよ」 「カレシは?」 「どうでしょうねー」 「その感じだとできてねぇな」 「・・・」 「ったくわかりやすすぎるっての。もっと嘘は上手くつけ」 「べっ、別に嘘はついてないもん。そっ、そういう高尾はどうなのよ」 「オレー?オレはなー、まぁ、いいだろンなもんどうだって」 質問の声が上擦ってまずいと思ったのも束の間、そんな曖昧な返答をされる。 それよりも、そんなのお前には関係ないって言われているような感じがして、距離を感じた。 幼馴染なんだし、聞いたっていいのかもしれない。 だけど幼馴染だからって何でも聞いていいわけじゃないだろう。難しいなと思う。 ただ、恋愛の話に関しては高尾としないほうが無難であることは確かだった。 だって話はいつも高尾のペースで、わたしは隠し事ができない。きっとボロが出る。 そんなことを考えていると、ふと胃のあたりに違和感を感じた。 おかしいなとわたしが思うのと、高尾が声をかけてきたのは同じくらいのタイミングだった。 いつもそう。高尾はすぐにわたしの異変に気付く。 「どうした?」 「んーごめんごめん、大丈夫。なんか昼頃からお腹の調子が良くなくって」 「お前、拾い食いでもしたんだろ」 「しないわよ!」 「まぁまぁ」 「まぁまぁじゃなくて!あ、もう家着いちゃった」 「おう、じゃーまた今度」 「うん、またね」 「お・だ・い・じ・に」 「うるさいなーじゃあね!」 こうやってふざけたやりとりばかりだけど。 『ちゃんとあったかくして寝ろよな』 部屋に入ってすぐに届いたメール。 こうやって気にかけてくれるから、万が一でも期待をしてしまう。 そうやって何年過ぎたかわからない。そろそろ潮時なんだろうなとは思っているんだけれど。 『うん。ありがとう』そう返信し、夕飯の支度をしに台所へ向かう。 それから、夕食の準備をしているうちに急激に具合が悪くなった。 急に食欲がなくなって、無理して少し食べた物も戻してしまった。 翌日病院へ行くと、疲れからくる急性胃腸炎との診断を受けた。 今日と明日は学校を休んだ方がよさそうと言われたため、学校にそう連絡を入れて自室のベッドで休む。 気持ちが悪くて起き上がることもままならず、とにかく眠ることと水分補給に徹した。 どれくらい眠っていただろうか。枕元の携帯からメールの着信を告げる音が鳴る。 手探りで携帯を探し当て、ぐちゃぐちゃの意識の中で画面を見つめる。 時刻は6時限目が終わったあたりだろうか、15時を過ぎていた。 『無事?』 高尾だった。 無事って何よと思うものの、目が回って文章を打つ気力もなかったわたしは、 『むり』 と、予測変換でなんとか打つ。 送信ボタンを押して、再び意識を手放した。 「ちょっと失礼しまーすって、おわっ、マジ死んでる」 あれからどれくらい寝ていたのかはわからない。 突然近くで高尾の声がして、枕に押しつけていた顔を横に向けゆるりと目を開く。 目の前にわたしを覗きこむ顔があって、それはぼんやりだったけど高尾に見えた。 「たかおー・・・?」 そう言うと、手が伸びてくる。その手はわたしの頭を撫でた。 その感じが気持ち良くて、わたしはふたたび目を閉じる。意識だけは全て手放さないようにだけして。 「なぁーに、お前そんな具合悪ぃの?」 「・・・・・・うん」 「反応悪すぎじゃね?」 「・・・・・・うん」 目を閉じていても安心していられるのはやっぱり高尾だからなんだと思う。 わたしの具合がもう少し良ければ、 「いちいち反応してられないくらい具合悪いんだってば」とか、「うつるから早く帰りなよ」とか、 いつもみたいに返したかったけれど、今のわたしにはそんな余裕なんて微塵もなくて。 もしこれ以上かまうつもりなら放っといてくれた方が良いなと一瞬思ったりもしたけれど、 わたしを撫でる手がやさしいから、もう全てどうでもいいかなって思えて、委ねて、甘えてしまいたくなった。 「なんか、お前が元気ねぇと調子狂うわ」 「・・・・・・うん」 「むり、とか返事よこすから、すげー心配になったっつーの」 「・・・・・・うん」 「早く良くなれよ」 「・・・・・・うん」 「うん以外言えねえのかよ」 「・・・・・・うん」 「・・・お前さ、オレのこと・・・」 わたしを撫でていた高尾の手が止まる。 その手は熱で熱くなったわたしの頬へするりと移った。 その手はすごく安心できて、気持ちよくて。 我ながら大胆な行動だと思ったけれど、その手に自分の手を重ねた。 これもきっと熱のせい。 「・・・・・・うん?」 うっすら目を開けて、高尾の顔を見た。 すると、バッとその手を引き抜かれる。 次の瞬間には高尾は一歩ベッドから遠のいていた。 「や、えっと、オ、オレ帰るわ。んじゃ、早く治せな」 そう言って、慌てたようにわたしの部屋を出て行った。 数時間後、薬が効いたのか体が比較的楽になっていた。 起き上がってみると、ベットの脇にコンビニの袋が置いてあるのが目に入った。 中を覗くと、飲むタイプのゼリーや栄養剤、ヨーグルトが入っていて、 ヨーグルトは高尾がすきなメーカーのだった。 メールを打ちかけて、画面を閉じる。 直接「ありがとう」と伝えたくて、そのヨーグルトを一口食べた。 |
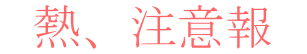 |
------------------------------------------------------------------ 様子を見に行き、自室へ帰ってきた高尾の独り言第一声。 「なんだよあのカオ・・・オレの理性崩れなくて良かった・・・病人は、マズイっつーの・・・」 ちなみに熱に浮かされていたので高尾が変な質問しようとしてたことは主人公覚えてませんっ。 高尾、ざんねん!がんばれ!あっ、もちろん親同士仲良しなのでお家も顔パスで入れます! わたしが胃腸炎で苦しんだ中で生まれたお話でした。ちゃんちゃん。 最後に、名前変換なくってすみません。 2013/1/22 なつめ close |